元VineのPMのプロダクトマネジメントに関する26の心得

元Vineでプロダクトのトップを勤めらていたJason Toff氏が、自身の経験から得たPMの心得みたいなものを、Mediamにまとめています。
自分自身に当てはめて、大変勉強になったので、より多くの人に伝わるよう、翻訳(意訳)してみました。
翻訳にあたっては、本人の許諾を得ています。
チームリーディングについて
ストーリーを持て
メンバが動かずにはいられなくなるストーリーを持ち、それを語ることがリーダとして一番大事
そのストーリーを繰り返せ
繰り返し伝えることは重要。もし、自分自身がそのストーリーを飽きるほど聞いていないのであれば、それは言い足りない
フォーカスすることはつらい
Vineでは、フォーカスするために2つのテクニックを利用した。
一つは、チームとして優先度の高い3つの事項を壁に書く
もう一つは、四半期ごとに各自の優先度の高いことを3つ書いてもらいスプレッドシートで共有した
週次の全体ミーティングはチームが同じ方向を向くために重要
本当に参加したくなるように設計する。一緒にVineをみたりスナックを食べたりしながらやった
週次で、優先度の高い事項3つをチームにメールで送る
常に最もインパクトのあることをするようにしろ
チーム文化はクリティカルに重要
会社というより、家族のように感じてもらえるように努力した
プロダクト開発について
ストーリー > 優先度
優先度のリストでは不十分。どうやってそれらをチームですり合わせる?最終的にどうやってそれらを組み立てる?プロダクトのストーリーは?
みんな最初は自分のためにプロダクトを作り出す
ユーザとプロダクトチームが重なっていることが理想だが、最初はユーザニーズとプロダクトチームは乖離している。ユーザスタディをチーム全体に開いた
ユーザニーズを近くで感じられるように、ヘビーユーザをチームに組み込む
責任を持つ個人を直接アサインする
どのプロダクトや機能も一人ではドライブできないが、結果に責任を持つ個人を置くべき。これがないと妥協が続く恐れがあるし、誰も最終的な結果に責任を持たなくなる
1,000人でテストできるならいきなり100万人にリリースするな
新機能は小さいユーザブループで試せ。モックでは得られない多くの気づきがある
何をやっているのか定期的に見せる場を設ける
デモの場を設けることで作っている人はモチベートされるし、残りの人はワクワクし、他の人が何をやっているのかを把握できる
賞賛しろ
賞賛することは人々をモチベートする最も効果的な方法だし、彼らを最高のバージョンに持っていく
チームメイトは、あなたが思っている以上にあなたをみている
あなたのレポートは、あなたが思っている以上に周りに影響を与える
解雇は必要悪
変な時間に仲間を邪魔しないように
これは失礼にあたる。Boomerangのメッセージで予定を組み込んだり、共有している1:1のドキュメントに追記するなりしろ
トップパフォーはクビになると恐れている
嘘のようで本当のはなし。必要としていることをフィードバックしてあげよう
採用について
個別の接触はかなり効果的
GoogleやFacebookとエンジニアを取り合っている場合、かなりタフな戦いになる。ギフトを贈ったりお祝いのメッセージを面接者から送ったりするといった個人的な接触は効果的
スピードが重要
数日以内に承諾してもらえるように努力する。時間は取引を無くしうる
採用マネージャからの短いメッセージは最高に高い返信率となる
リクルーターからの普通のメールより、責任者からの短いメールの方が効果的
その他
いいスピーチには練習が必要
クリエイティブになる余裕を自分に与える
連続したミーティングはこれを難しくする。30分の休憩はさらに悪いだろう。カレンダーをコントロールし、カレンダーにコントロールされないように
実際に自分の中で成功体験があることと、実践できていないけど効果がありそうだなと思うことの両方があり勉強になりました。
PMは考えるべきことが多い仕事ですが、その分やりがいもあると思います。
おすすめのPM本

- 作者: マーティケイガン
- 出版社/メーカー: 株式会社 マーレアッズーロ
- 発売日: 2015/02/07
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログ (1件) を見る
ランサーズで施策検討する際に利用している企画書フォーマット
私が勤務しているランサーズでは、施策検討の際に、ディレクター陣で共通のフォーマットを利用して企画ドキュメントを作成しています。
最近、どうやって施策検討しているのか聞かれることが増えてきたので、フォーマットをご紹介させていただきます。
ちなみにドキュメントはコンフルエンスにまとめています。
なぜ企画フォーマットを用意するのか
誰が書いても一定の品質を保てるように
施策を検討する際には、押さえるべきポイントがあり、それらを漏れなく検討することが重要です。
フォーマットを用意して、各項目を埋めてもらうことで、抜け漏れを防ぐことができるようになります。
また、入社直後のディレクターでも、フォーマットに沿って書くことで、最低限のレベルを担保することができますし、学習しやすいという効果があります。
レビュアの負荷軽減
毎回違うフォーマットだと、レビューする側に理解の負荷が発生します。
フォーマットを統一しておくことで、少なくとも項目や流れは変わらないので、確認しやすいというメリットが生まれます。
企画書の項目
概要
施策内容を5W1Hで端的に説明します。
レビュアやエンジニア・デザイナが、ぱっと見でこの企画を理解できるようにすることが目的です。
背景/目的
その施策を企画するに至った背景や達成したい目的。
ターゲットユーザを想定し、誰の何の課題を解決するのかを書く。
現状の課題
現状の課題を、ユーザ目線、運営目線など多面的に列挙する。
解決策
現状の課題を解決する方法。これが施策内容となります。
複数案出し、メリデメや効果工数などの評価軸で絞っていきます。
ターゲットKPIと目標値・撤退ライン
ターゲットKPIを明確にし、現在値、目標値、撤退ラインを決める。
撤退ラインを決めておくことが重要で、その数値を下回ったら、思い切って戻すことを決めておく。
取得方法(SQLクエリやGAのリンク)やモニタリングシート(スプレッドシート等のURL)も記載しておきます。
参考サービス調査
似ている施策が他のサービスにあれば、サービス名とキャプチャ・仕様などをまとめる。
いかに多くのサービスや引き出しがあるか、ディレクターの知識の見せ所。
UI
ワイヤを添付
仕様
仕様をテキストで記述。ワイヤ内に吹き出しなどで記述しても可。
デザイン
ワイヤから作成したデザイナカンプを添付。いきなりプロトタイプ作成の場合はなくても良い。
リリース後プロモーション
リリース後のユーザ告知方法や、効果を最大化するためのプロモーション方法を記述。
告知に当たっての必要な関係部署への連携も意識しておく。
他部署連携
ユーザサポートや広報など、事前連絡が必要な部署と連絡内容を記述。
スケジュール
小さい施策であれば箇条書きで日付とマイルストンをドキュメント内に書く。
大きめの施策の場合は、スプレッドシートで線表などを作成してリンクを貼る。
体制
施策に必要な役割と担当者を記述。
過去の関連施策(あれば)
過去に実施した関連施策があれば記述。
実施効果や、やめた場合はその理由など背景があると良い。
将来的な追加機能/発展
今後の追加機能実装や、効果が出ない時のバックアッププランなどを記述。
未経験でもサービスの企画ができるようになります!
本記事で紹介したフォーマットなど、ディレクターを育成する仕組みがランサーズにはあります。
Webサービスやアプリを作れるようになりたいという方、積極的に採用していますので、ご興味ありましたら下記をご覧の上、ご応募お待ちしております!
www.wantedly.com
Webサービスリリース後1ヶ月の会員登録数やPV

5月8日に、最新のWebサービスやアプリのキュレーションサービス『Service Safari』をリリースしました。
リリースから1ヶ月が経ったので、リリース後どういったことをやってきて、その結果ユーザ数やPVといったKPIがどうなったのかをまとめたいと思います。
主要数値
会員登録することで、毎朝メールで最新情報が受け取れるという点を売りにしていたので、会員登録はなるべくしてほしいなと思って一番気にしていました。
- 会員登録数 868人
- 5,131UU
- 19,636PV
会員登録1,000、2万PVを目標としていたので、残念ながら未達となりました。
会員属性の特徴として、やはりスタートアップやWeb系企業が多く占めているのが特徴です。特に面白いのが、投資家の方や経営者の方が多いことです。やはりアンテナを高く伸ばしているんですね。
やったこと
キュレイターコミュニティの形成
Service Safariは、厳選されたキュレイターが最新のサービスを投稿し、それをユーザがメールで受信できる、という点に価値を置いているため、キュレイターの方々は、サービス上とても大切です。
元々知り合いのサービス感度の高い方だけでなく、Service Safariに登録してくれた方で、感度の高そうな方を積極的にスカウトさせて頂きました。
また、キュレイターの交流会を開催し、なぜService Safariを創ったのかを共有させていただき、サービスへの理解を深めて頂くように心がけました。
キュレイターの方のFacebookグループを作成し、サービスへの改善要望を受け付け、共創感の醸成もしています。
登録されたサービスの運営元への連絡
新しいサービスが登録される度に、そのサービスを運営されている方にご連絡しました。
投稿されたサービスに投票ができ、投票数が多いとページ上部に表示される、メルマガで一番上に掲載される(約1,000人にリーチ)といったメリットがあるので、掲載されたサービスの中の方が会員登録してくれたり、友人に拡散をしてくれたりして会員登録が伸びました。
ブログでの情報発信
僕も共同運営者も個人でブログを書いているため、積極的にブログで情報発信を行いました。結果、ブログでサービスを知ってくれた新規ユーザが多く増えました。
2日間でWebサービスをリリースするまでにやったこと全て - No Web Service No Life
こう振り返ってみると、結構アナログというか泥臭いことが効果がありました。Webサービスといえど、地道な施策は侮れないなと改めて実感しました。
今後やろうと思っていること
上に書いたようにいくつか施策を実施しましたが、本格的なグロースハックは未着手で、まだやれることは多くあると思っています。
SNS連携強化
Service Safariの利用を開始したことをSNSでシェアする、新しいサービスを投稿したらSNSにも流すなど、SNSにもっと情報が発信されやすくする仕組みを組み込めると思っています。この辺りは、今後作っていきたいと思っています。
SEO
リリース当初は、テキストコンテンツが多くないサービスなので、オーガニック流入は期待していませんでした。しかし、意外と非指名ワードでの流入が多く、日々伸びてきているので、SEOも流入チャネルとして伸びしろがありそうです。
具体的には、カテゴリ一覧ページの強化とTDの改善です。現時点では、検索順位とSERPへの表示回数の割にクリック数が少ないので、TDを改善しCTRを上げることで流入まで結びつけたいと思っています。
会員登録CVRの向上
SNSやSEOで流入した新規ユーザを会員化するために、会員登録CVRの向上も合わせて実施します。具体的には、ID連携可能なサービスの拡充(現時点ではFacebookとTwitterのみ)や、登録メリットの創出、訴求を実施予定です。
上記の施策を実施し、今月こそは、単月で会員登録数1,000、PV2万を達成したいと思います。
まだ会員登録されていない方は、毎朝最新のサービス情報がメールで届きますので、ぜひともご登録頂ければと思います!
Service Safari | 最新サービスのキュレーション Service Safari
最新情報は、Service SafariのFacebookやTwitterでも発信しております。
キュレイターも募集していますので、サービスに詳しい方はぜひともご連絡いただければ幸いです!
↓私個人の連絡先
Facebook:https://www.facebook.com/kkino0927
Twitter:https://twitter.com/kei_kinoshita
2日間でWebサービスをリリースするまでにやったこと全て

5/8に、最新のWebサービスやアプリの投稿サイト『Service Safari』を、友人と一緒にリリースしました。
海外に参考となるサービスがあり、これは便利!日本版も欲しい!と思ったのが開発のきっかけです。
元となるサービスがあったこともあり、つくりたい!と思ってから2日間でリリースすることができました。
今回は、着想からリリースまでにやった、以下の作業についてまとめてみたいと思います。
- 企画
- UI設計
- 開発
- リリース準備
- 事前マーケティング
体制
僕とエンジニアの2人体制です。
エンジニアは、学生時代からの付き合いの@eiei19で、全て一人で開発してくれました。
僕:企画、UI設計、マーケティング
eiei19:開発
といった役割分担です。
企画
前述の通り、既に参考となるサービスがあったので、基本的には仕様も踏襲させていただきました。
今後の展開も考えて、データはこういう風に持っていた方がいいよね、とかは考えていましたが。
UI設計・デザイン
UIも本家と似ているのですが、一応色味とかはオリジナリティ出したいなぁと思って考えました。
エクセルでワイヤを書いて、吹き出しで仕様を書く、といったベーシックなやり方です。

開発
cleardb、RoR、Herokuという構成です。ホスティングにはBitbucketを使っています。
理由は、プライベートリポジトリが無料なのと、僕がAtlassianが好きだからです。
詳しくはこちらにまとまっています。
最新サービスのキュレーション、Service Safariをリリースしました!! | ITANDI技術ブログ
リリース準備
プログラミングをしただけではリリースできないので、他にも細かな準備をしました。
ドメイン取得
ドメインはお名前.comで取っています。ちょうどその時、千葉県の鴨川市を旅行していたので、LTEが入らないローカル喫茶店でスマホでドメインを取りました。まさか鴨川でドメインを取得するとは思っていなく、時代は変わったなぁと思いました。後にも先にも、あの喫茶店でドメインを取得したのは僕だけだと思います。
鴨川のローカル喫茶店の場所

メールの設定
Service Safariには、最新の投稿されたサービスをメルマガ形式で配信するという機能があり、そのためにメールの設定が必要でした。
自前でPostfix等を入れてもよかったのですが、手軽さから、Google Appsを利用しています。メール配信は、AWSのSESを利用しています。
事前マーケティング
Webサービスは、リリース時の拡散が大切です。リリース時にいかにユーザを獲得できるかが、その後の成長に大きく影響してきます。
今後の展開
参考となる海外サービスがあり、それの日本版としてスタートしたService Safariですが、今後はオリジナル色も出していこうと思っています。
少なくとも、日本のサービス・アプリが全て集まっているデータベースとし、サービスについてはService Safariをみていれば十分、という地位まで持って行こうと思っています。
まだまだリリースしたてで、改善の余地が多くありますが、引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします!
キュレイターをやりたい!自分のサービスを載せて欲しい!などありましたら、私までご連絡の程、よろしくお願いいたします。サービス改善要望も受け付けております。
Facebook:https://www.facebook.com/kkino0927
Twitter:https://twitter.com/kei_kinoshita
Webディレクターはサービスサファリに出かけよう!
Webサービスを企画する人は、自分が企画している製品を積極的に使おう、というお話です。
サービスデザイン
Rosenfeldという、UXコンサルと関連書籍の出版をしている会社がアメリカにあります。
モバイルフロンティアやメンタルモデルの出版元であり、UXデザインにおいてとても参考になる良書を数多く出版している会社です。
そんなRosenfeld本の日本語で読める書籍の最新版として、5月1日に、「サービスデザイン」という書籍が邦訳、発売されます。

サービスデザイン ユーザーエクスペリエンスから事業戦略をデザインする
- 作者: Andy Polaine,Lavrans Løvlie,Ben Reason,長谷川敦士
- 出版社/メーカー: 丸善出版
- 発売日: 2014/05/01
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
大好きなRosenfeldから、サービスデザインに関する書籍が発売になると知ってから、サービスデザインというものに興味を持っています。
既に日本語で読めるサービスデザインに関する書籍として、「THIS IS SERVICE DESIGN THINKING.」という本があります。本書では、色々なサービスデザインツールが紹介されており、その中の1つである「サービスサファリ」が納得感があったので、その理由をまとめてみます。

THIS IS SERVICE DESIGN THINKING. Basics - Tools - Cases ー 領域横断的アプローチによるビジネスモデルの設計
- 作者: マーク・スティックドーン,ヤコブ・シュナイダー,長谷川敦士,武山政直,渡邉康太郎,郷司陽子
- 出版社/メーカー: ビー・エヌ・エヌ新社
- 発売日: 2013/07/25
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (1件) を見る
※サービスデザインについての説明は、こちらをご参照ください。
サービスサファリとは
THIS IS SERVICE DESIGN THINKINGでは、以下のように説明されています。
参加者が「実世界」で実際にサービスを体験し、良いサービスと悪いサービスの事例を集める技法です。
僕自身、Airbnbであれば実際に宿泊したり、Buymaであれば実際にブランド品を購入したりしています。単純にサービスを眺めたり、会員登録したりしただけでは、サービス設計やそこから生み出されるUXは理解できないと思っているからです。
良いUXを作るには、色々なサービスのUXを体感し、良いもの多く触れることが重要です。
そんなサービスサファリでも、特に、自社サービスを利用することが、企画をするWebディレクターにとって重要だと感じています。
自社サービスサファリが重要な理由
UXの実体験
他サービス同様、UXを実感しようと思ったら、自ら使ってみるしか方法はありません。ディレクターとしてサービスのUX向上をミッションとしている以上、自社サービスのUXを実感することが必須です。
サービスの課題の発見
実際に使っていくことで、サービス上の課題を発見することができます。
個別の機能を実装していくと、全体としての統一感やフローで利用した場合の違和感に気づきにくくなります。そんな時、定期的にサービスを利用し、フローとしての整合性を確認することが大切になってきます。
ユーザさんとのサービス上での交流
サービスを利用するだけであれば、開発環境でも実現可能です。しかし、本番環境で利用することによって、そこにいるユーザさんとのリアルな交流が可能となります。
ランサーズのようなクラウドソーシングサービスであれば、以下の様な体験をすることが重要です。
- どのような案件が実際に依頼されており、受注者として提案するとどういった体験をするのか。落選した時はどうか、当選したときはどうか
- 発注者として依頼してみたとき、どのような提案が集まり、どのような成果物が納品されるのか。その過程でのやりとりはどういったものなのか
自らが発注者・受注者双方を経験することによって、どういった対応をされると嬉しい(=UXの向上)のか、逆にどういった対応をされると嫌な思いをする(=UXの低下)のかを理解することができ、それを防ぐ・和らげるための打ち手を実体験をベースに考えることができます。また、細かいUI改善ポイントも多く発見することができます。
ランサーズは、発注にお金がかかるサービスなのですが、身銭を切ってでも、自社サービスのリアルを体験することは重要ですので、今後も継続的に利用していきたい思います。
エンジニアからディレクターに転身してから読んだ本14冊
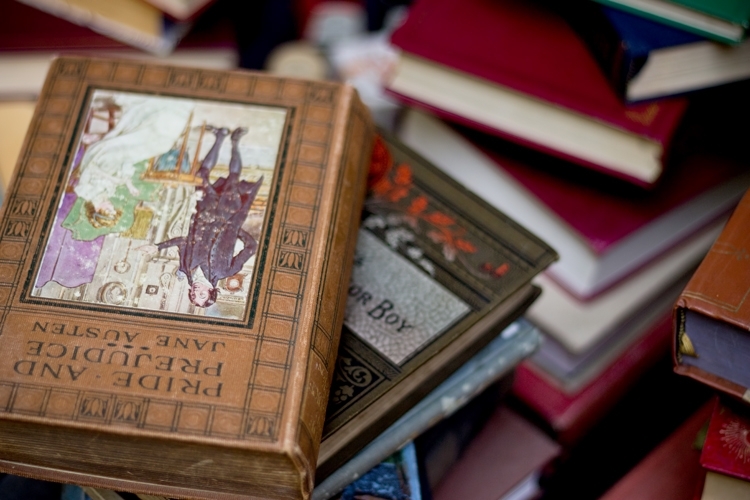
私は、元々エンジニアとしてランサーズに入社し、途中からディレクターに転身しました。ランサーズに入社する以前は、Googleアナリティクスをいじったこともなければ、CVRやCPAといった基本的なマーケティング用語すら知りませんでした。
まだまだ知識・スキル不足ではありますが、今まで得たものの多くは実際の業務を通して得られました。一方で、書籍を読むことで以下の二つのメリットがあると感じており、読書の時間を取るように努めています。
- 業務で得たスキル・知識を体系的に整理して定着させる
- そもそも知らないことをショートカットして知ることができる
ディレクターに転身してから、必要な知識を身につけるために読んだ本を、ジャンル別にご紹介します。
Webエンジニアの時のおすすめ書籍は下記にまとめてあります。
kkino.hatenablog.com
基本的なビジネススキル
どの職種においても必要なスキルだと思います。特に、ディレクターは、分析をしたり、方針を決めたり、それらを人に伝えたり、会議体を運営したりと、幅広いビジネス推進力が必要になる職種の一つだと思います。
これらをスピーディーに進めるために、ロジカルシンキングやデータ分析、コミュニケーション手法など、標準的なビジネススキルを最初に得ておくことは、その後の仕事進行において非常に重要になります。

- 作者: グロービス経営大学院,田久保善彦,村尾佳子,鈴木健一,荒木博行
- 出版社/メーカー: 東洋経済新報社
- 発売日: 2014/08/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
サービス企画
そもそも、サービスの企画とはどのように進めていけばいいのか?ディレクターに求められるスキル、知識とは何なのか?を解決してくれた3冊です。

Webディレクション標準スキル152 企画・提案からプロジェクト管理、運用まで
- 作者: 日本WEBデザイナーズ協会
- 出版社/メーカー: アスキー・メディアワークス
- 発売日: 2012/03/15
- メディア: 大型本
- 購入: 2人 クリック: 42回
- この商品を含むブログ (5件) を見る

ユーザ中心ウェブサイト戦略 仮説検証アプローチによるユーザビリティサイエンスの実践
- 作者: 株式会社ビービット武井由紀子,遠藤直紀
- 出版社/メーカー: ソフトバンククリエイティブ
- 発売日: 2006/09/27
- メディア: 単行本
- 購入: 14人 クリック: 313回
- この商品を含むブログ (47件) を見る

Webサイト設計のためのペルソナ手法の教科書 ~ペルソナ活用によるユーザ中心ウェブサイト実践構築ガイド~ (DESIGN IT!BOOKS)
- 作者: Ziv Yaar,Steve Mulder,佐藤伸哉,奥泉直子
- 出版社/メーカー: 毎日コミュニケーションズ
- 発売日: 2008/02/23
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 1人 クリック: 46回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
UX
Webサービスやアプリが簡単に立ち上げられるようになり、多くのサービスが存在している昨今、差別化要因となるのはUXです。
UIや使い勝手といった、プロダクトとユーザの接点だけではなく、プロダクトを中心とした広い世界での体験が重要になってきています。

ウェブ戦略としての「ユーザーエクスペリエンス」―5つの段階で考えるユーザー中心デザイン (Web designing books)
- 作者: Jesse James Garrett,ソシオメディア
- 出版社/メーカー: 毎日コミュニケーションズ
- 発売日: 2005/02
- メディア: 単行本
- 購入: 3人 クリック: 133回
- この商品を含むブログ (18件) を見る

Lean UX ―リーン思考によるユーザエクスペリエンス・デザイン (THE LEAN SERIES)
- 作者: ジェフ・ゴーセルフ,坂田一倫,ジョシュ・セイデン,エリック・リース,児島修
- 出版社/メーカー: オライリージャパン
- 発売日: 2014/01/22
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (2件) を見る

モバイルフロンティア よりよいモバイルUXを生み出すためのデザインガイド
- 作者: 安藤幸央,佐藤伸哉,青木博信,清水かほる,野澤紘子,羽山祥樹,脇阪善則
- 出版社/メーカー: 丸善出版
- 発売日: 2013/04/25
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (2件) を見る
UI・デザイン
エンジニアからの転身ということもあり、自分が弱い部分である一方で、Webサービスにおいて重要な部分なので、一番注力して勉強している領域です。ユーザが触れるのはUIなので、いいUXを生み出すためにも、UIデザインは重要です。

誰のためのデザイン?―認知科学者のデザイン原論 (新曜社認知科学選書)
- 作者: ドナルド・A.ノーマン,D.A.ノーマン,野島久雄
- 出版社/メーカー: 新曜社
- 発売日: 1990/02
- メディア: 単行本
- 購入: 37人 クリック: 945回
- この商品を含むブログ (289件) を見る

インタフェースデザインの心理学 ―ウェブやアプリに新たな視点をもたらす100の指針
- 作者: Susan Weinschenk,武舎広幸,武舎るみ,阿部和也
- 出版社/メーカー: オライリージャパン
- 発売日: 2012/07/14
- メディア: 大型本
- 購入: 36人 クリック: 751回
- この商品を含むブログ (28件) を見る
![ノンデザイナーズ・デザインブック [フルカラー新装増補版] ノンデザイナーズ・デザインブック [フルカラー新装増補版]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41nvddaG9BL._SL160_.jpg)
- 作者: Robin Williams,吉川典秀
- 出版社/メーカー: 毎日コミュニケーションズ
- 発売日: 2008/11/19
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 58人 クリック: 1,019回
- この商品を含むブログ (106件) を見る
Web制作に関わる全ての人は「ノンデザイナーズ・デザインブック」 を読むべき - No Web Service No Life

- 作者: 佐藤直樹,ASYL
- 出版社/メーカー: グラフィック社
- 発売日: 2012/06/06
- メディア: 単行本
- 購入: 2人 クリック: 22回
- この商品を含むブログを見る
SEM・アクセス解析
ディレクター業務の中で、一番好きな分野です。一日中GAをみていても飽きません!

- 作者: 阿部圭司
- 出版社/メーカー: ソーテック社
- 発売日: 2013/03/28
- メディア: 単行本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
SEM-LABO | SEMマスターによるSEMラボ!・アクセス解析・リスティング広告ブログ

- 作者: 渡辺隆広
- 出版社/メーカー: 翔泳社
- 発売日: 2008/06/17
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 7人 クリック: 373回
- この商品を含むブログ (15件) を見る
[SEM R] :: 検索エンジンマーケティングのことなら SEMリサーチ

入門 ウェブ分析論 ―― アクセス解析を成果につなげるための新・基礎知識 増補改訂版
- 作者: 小川卓
- 出版社/メーカー: ソフトバンククリエイティブ
- 発売日: 2012/03/22
- メディア: 大型本
- 購入: 2人 クリック: 13回
- この商品を含むブログ (11件) を見る

- 作者: 小川卓
- 出版社/メーカー: 翔泳社
- 発売日: 2012/08/17
- メディア: 大型本
- 購入: 1人 クリック: 6回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
データ分析
ディレクターにとって、データ分析は非常に重要スキルです。
実施した施策の効果測定だけでなく、そもそも施策を検討する段階でも、データ分析による現状把握は不可欠だからです。

- 作者: あんちべ
- 出版社/メーカー: 森北出版
- 発売日: 2015/06/20
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (3件) を見る
他にも多くの本を読みましたし、もちろんブログやメディアといったWebの情報も多いに参考にしています。
また、書籍だけでなく、人から得られる情報も非常に素晴らしく、多くの先輩ディレクターの方々に教えを乞うてきました。
これからも精進したいと思います。
ランサーズで実践しているWebサービスの企画プロセス ~情報収集編~

Webサービスを企画するにあたって必要な作業を、数記事にわたって書いていきたいと思います。
まずは情報収集からです。情報が不足していたり誤っていたりすると、後々の工程に影響が出ますので、重要な作業となります。
情報の発生元別に、内部情報・外部情報に大別してご説明します。
内部情報
内部情報とは、サービスや社内から取得できる情報で、外部から取得できない情報です。
全社方針
ビジョンや経営戦略、事業戦略のことを指します。いかなる新サービス、新機能をつくるときでも、これはビジョンに沿っているのか?ユーザのためになるか?今の全社戦略に沿っているか?は常に確認します。
仮説
収集する情報というよりは、自分で持っている考えです。サービスを運営していて感じている課題やその原因に対する仮説です。長くサービスに触れていると肌感覚で分かるものがあり、概ねあっているのでは?と思っています。
データ
アクセスログやサービスKPI、ヒートマップといった定量的に計測可能な指標です。(きちんと取得できていれば)データは嘘をつきません。圧倒的な信頼性を持つデータをしっかり計測し、企画の根拠にすることは重要です。
顧客の声
良いUXにおいて、サービスの主体はユーザです。たとえ母数が1人だとしても、ユーザが感じていることを真摯に受けとめ、企画に盛り込むことはユーザ第一主義の観点から重視しています。
実際のサービス企画においては、仮説を検証するために、データや顧客の声を参照するという順番を取っています。仮説なくデータや顧客の声をみると、量が多すぎて時間がかかりすぎるので、ある程度仮説をもって絞り込んで調査しています。